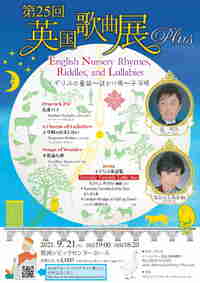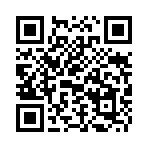2014年12月09日
≪生誕100年≫フェレンツ・フリッチャイ Ferenc Fricsay
フェレンツ・フリッチャイ Ferenc Fricsay
1914.8.9/ブタペスト(ハンガリー)~1963.2.20/バーゼル(スイス)
フリッチャイはドイツを中心に活躍し、48歳の時に白血病で亡くなった指揮者である。2013年は没後50年、2014年は生誕100年ということで、数々の記念CDがドイツ・グラモフォンやタワーレコードから発売された。
●≪没後50年企画≫2013/3/8発売・タワーレコード「フェレンツ・フリッチャイの芸術」第1期/ベートーヴェン: 交響曲選集 http://tower.jp/item/3210068/
初回販売版は商品不良との連絡があったのですが、せっかくなので交換せずに記念品として保管。

●≪生誕100年企画≫2014/7/8発売・ドイツ・グラモフォン『フェレンツ・フリッチャイ/DGレコーディングズ全集Vol.1~管弦楽曲編』 http://tower.jp/item/3629174/

この二度とない機会に、フリッチャイを偏愛している私個人の想いを、ここに書き留めておきたい。
初めてフリッチャイの演奏を聴いたのは、ベートーヴェン交響曲第9番のCDだった。名古屋栄のPARCOに入っていたタワーレコードだっただろうか、表紙に惹かれ手にしたところ、ソリストがヘフリガーとディースカウ、そして「ステレオ録音」と書いてある。これが決め手となり購入した。
●ベートーヴェン交響曲第9番≪合唱≫(1993/11/1発売・DG Ferenc Fricsay Edition)
ゼーフリート(S) フォレスター(A)ヘフリガー(T)フィッシャー=ディースカウ(Br)
聖ヘトヴィッヒ大聖堂聖歌隊
フリッチャイ(指揮) ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団
1957年12月、1958年1月・4月 ベルリン・イエスキリスト教会

当時は奇想天外な、個性的な演奏がばかり聴いていたので「特徴のない、退屈な演奏」としか思えず、一度聴いたきりだった。(今では数ある第九CDの中で最も愛する演奏のひとつ)
その後しばらくして、宇都宮の新星堂でドヴォルザーク交響曲第9番のCDを手に取った。その頃≪新世界より≫を気に入って聴いていたので購入したのだと思うが、思いがけずその演奏にしびれてしまった。特に3楽章のリズム感の凄さ、これは指揮者の能力によるものと確信した。(カルロス・クライバーのブラームス交響曲第4番を聴いたときと同様の衝撃だった。)4楽章冒頭の表現にもひっくりかえった。こんなのあり?という驚き。
●ドヴォルザーク交響曲第9番≪新世界より≫(1996/11/21発売・DG LEGEND)
フリッチャイ(指揮) ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団
1959年10月 ベルリン・イエスキリスト教会

それからは、フリッチャイのCDを探し蒐集する日々。1961年のベートーヴェン交響曲5番の崇高な響きと佇まいに夢中になり、何度も聴いた。第1番も新鮮かつ生命力溢れる名演である。指揮者の意向でお蔵入りになっていたとされる1959年のチャイコフスキー交響曲第6番は信じられないほど凄い演奏。その深みのある音色に引きずり込まれた。(こちらは凄演すぎて繰り返し聴けない・・・)
様々な録音に接して思うのは、演奏の集中力に意外とばらつきがあること。録音時期によることも承知しているが、霊的な凄みを感じる演奏もあれば、思いのほか淡白な演奏もある。しかし、これらについても彼の人間性を想い起こさせ、より惹かれてしまう要因になっているのだ。そして、芳醇な響きや色彩を生み出す卓越したバランス感覚、作品に生命力を与えるリズム感は他に類を見ないと思う。バルトークの教えを受け、その演奏において第一人者であったことも理由にあろう。音楽に向かう真摯な姿勢、根源的な魅力でもって共演者を惹きつけてしまう音楽的才能と人間性を、演奏から窺い知ることができる。
批判を受けることを承知の上で言うと、カルロス・クライバーと同列の天才性をもっていたのではあるまいか。ただし、演奏の性格は異なるし、フリッチャイはもう少し我々に寄り添った位置にいたのかもしれない。
前述『フェレンツ・フリッチャイ/DGレコーディングズ全集Vol.1~管弦楽曲編』は、1949-1961までの記録である。この短い期間に管弦楽作品のみでCD45枚分を収録したことは、ステレオへの改変期であったレコード会社の期待の大きさの表れであるし、ハイドンから当時の現代音楽までというレパートリーもその演奏水準からすると尋常ではない幅広さだ。
あらためて、その才能と人間に想いを馳せる。1914年生まれの指揮者はラファエル・クーベリック、カルロ・マリア・ジュリー二がいる。彼らと同じように、もっと長く生きて演奏活動を続けて欲しかった。私の愛する指揮者は、ユージン・オーマンディ、イシュトヴァン・ケルテス、いずれもハンガリー出身の指揮者である。
1914.8.9/ブタペスト(ハンガリー)~1963.2.20/バーゼル(スイス)
フリッチャイはドイツを中心に活躍し、48歳の時に白血病で亡くなった指揮者である。2013年は没後50年、2014年は生誕100年ということで、数々の記念CDがドイツ・グラモフォンやタワーレコードから発売された。
●≪没後50年企画≫2013/3/8発売・タワーレコード「フェレンツ・フリッチャイの芸術」第1期/ベートーヴェン: 交響曲選集 http://tower.jp/item/3210068/
初回販売版は商品不良との連絡があったのですが、せっかくなので交換せずに記念品として保管。

●≪生誕100年企画≫2014/7/8発売・ドイツ・グラモフォン『フェレンツ・フリッチャイ/DGレコーディングズ全集Vol.1~管弦楽曲編』 http://tower.jp/item/3629174/

この二度とない機会に、フリッチャイを偏愛している私個人の想いを、ここに書き留めておきたい。
初めてフリッチャイの演奏を聴いたのは、ベートーヴェン交響曲第9番のCDだった。名古屋栄のPARCOに入っていたタワーレコードだっただろうか、表紙に惹かれ手にしたところ、ソリストがヘフリガーとディースカウ、そして「ステレオ録音」と書いてある。これが決め手となり購入した。
●ベートーヴェン交響曲第9番≪合唱≫(1993/11/1発売・DG Ferenc Fricsay Edition)
ゼーフリート(S) フォレスター(A)ヘフリガー(T)フィッシャー=ディースカウ(Br)
聖ヘトヴィッヒ大聖堂聖歌隊
フリッチャイ(指揮) ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団
1957年12月、1958年1月・4月 ベルリン・イエスキリスト教会

当時は奇想天外な、個性的な演奏がばかり聴いていたので「特徴のない、退屈な演奏」としか思えず、一度聴いたきりだった。(今では数ある第九CDの中で最も愛する演奏のひとつ)
その後しばらくして、宇都宮の新星堂でドヴォルザーク交響曲第9番のCDを手に取った。その頃≪新世界より≫を気に入って聴いていたので購入したのだと思うが、思いがけずその演奏にしびれてしまった。特に3楽章のリズム感の凄さ、これは指揮者の能力によるものと確信した。(カルロス・クライバーのブラームス交響曲第4番を聴いたときと同様の衝撃だった。)4楽章冒頭の表現にもひっくりかえった。こんなのあり?という驚き。
●ドヴォルザーク交響曲第9番≪新世界より≫(1996/11/21発売・DG LEGEND)
フリッチャイ(指揮) ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団
1959年10月 ベルリン・イエスキリスト教会

それからは、フリッチャイのCDを探し蒐集する日々。1961年のベートーヴェン交響曲5番の崇高な響きと佇まいに夢中になり、何度も聴いた。第1番も新鮮かつ生命力溢れる名演である。指揮者の意向でお蔵入りになっていたとされる1959年のチャイコフスキー交響曲第6番は信じられないほど凄い演奏。その深みのある音色に引きずり込まれた。(こちらは凄演すぎて繰り返し聴けない・・・)
様々な録音に接して思うのは、演奏の集中力に意外とばらつきがあること。録音時期によることも承知しているが、霊的な凄みを感じる演奏もあれば、思いのほか淡白な演奏もある。しかし、これらについても彼の人間性を想い起こさせ、より惹かれてしまう要因になっているのだ。そして、芳醇な響きや色彩を生み出す卓越したバランス感覚、作品に生命力を与えるリズム感は他に類を見ないと思う。バルトークの教えを受け、その演奏において第一人者であったことも理由にあろう。音楽に向かう真摯な姿勢、根源的な魅力でもって共演者を惹きつけてしまう音楽的才能と人間性を、演奏から窺い知ることができる。
批判を受けることを承知の上で言うと、カルロス・クライバーと同列の天才性をもっていたのではあるまいか。ただし、演奏の性格は異なるし、フリッチャイはもう少し我々に寄り添った位置にいたのかもしれない。
前述『フェレンツ・フリッチャイ/DGレコーディングズ全集Vol.1~管弦楽曲編』は、1949-1961までの記録である。この短い期間に管弦楽作品のみでCD45枚分を収録したことは、ステレオへの改変期であったレコード会社の期待の大きさの表れであるし、ハイドンから当時の現代音楽までというレパートリーもその演奏水準からすると尋常ではない幅広さだ。
あらためて、その才能と人間に想いを馳せる。1914年生まれの指揮者はラファエル・クーベリック、カルロ・マリア・ジュリー二がいる。彼らと同じように、もっと長く生きて演奏活動を続けて欲しかった。私の愛する指揮者は、ユージン・オーマンディ、イシュトヴァン・ケルテス、いずれもハンガリー出身の指揮者である。